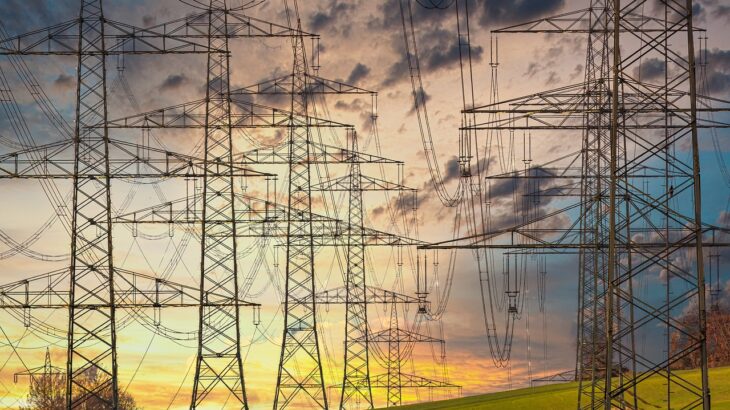資格の中では受験者が圧倒的に多い、電気工事士第2種。人気資格という言葉に釣られ、受けようと思いましたが、受けるまで1か月くらい悩んだかもしれません。
今、思えば無駄にしか思えないんですが、やっぱりたかが
資格と言えど、挑戦するのは怖い。
落ちたら、笑われるとか思うわけですよ。高校生で取ってる人もいるわけですから。でも、そんなのは、せこいですが受けたことを誰にも言わなければいい。それよりも、なんでしょう。
おそらく落ちた時に、それまでしてきた努力が無駄になってしまうのがもっと怖かったのかもしれません。
合格率はそれほど低くないものの、筆記試験(9月実施)と実技試験(12月実施)があるので、試験勉強をする期間はそれなりに時間を取らないといけないんですよね。同じ日に試験が実施されるなら、まだ中だるみしなくていいんですが、筆記試験で受かってからのモチベーションを保つのも結構しんどかったイメージがあります。
あと、筆記でやった事が実技で結構活かされるかと思いきや、、、
こんな事言っちゃなんですが、記号さえ覚えてれば、筆記が実技で活かされることは、あんまりないなと思っちゃいましたね。そのくらい別物だと思って、試験に挑んだ方が良いかも知れません。
電気工事士第二種の筆記試験の勉強方法
僕に関して言うと、電気に関しての知識は、少しはあるという程度のものではなく、全くないという状態から入ったと言っても過言ではありません。
参考書を見ても、ちんぷんかんぷん。かろうじて分かる単語が、電流と電力、抵抗くらいのものです。単語は聞いたことはあっても、意味は全くもって分からない状況から始めました。そんな状況からでも2か月程度で92点取れてるので、経験あるかどうか、知識はどの程度なのかを資格を取る前から気にして、受けるかどうかを迷うのはもったいないです。
僕は、電気工事士2種なら迷わず受けろ!と言いたいですね。
筆記試験を受けるにあたって、購入したものは参考書一冊。
実際に読んでみると分かりやすいとは思いましたが、この本を丸々一冊真剣に読んだかと言うと、ほとんど読んでません。この参考書に関していうと、まず、電線の種類や道具、記号など画像があるものを覚えていった程度です。

この「一回で受かる」というキャッチコピーに惹かれ購入しました。道具などはカラー画像で掲載されるので、とても覚えやすいのですが、途中から始まる基礎部分からは、画像、イラストもありません。文章が多いので独学で勉強するとなるとちょっと覚えにくいかも。
それ以外はどのように使ったかというと、アプリの問題を解いていって、分からないところは参考書と一緒に確認する。
これをひたすら繰り返しました。2か月間ね。
電気工事士に関しては、参考書を何度も読んで覚えるというやり方はあまり適さないように思います。とにかく問題を解く。分からなかった問題は参考書で調べてみる。しかし、このやり方でも、問題自体の意味が分からなかったり、参考書のどのページに記載されているのか分からない場合があります。
そういう時は、僕は完全に飛ばしてました。
でも、そうやって何度もアプリの問題を解くうちに、結構分かってきます。あと、電気工事士の筆記試験ではアプリでは解決しがたい、複線図の問題があります。複線図は独学でやろうとすると、難解です。
しかし、実は考え方を変えると、、
実は筆記試験で複線図の問題は50問中3,4問しか出ないんですよね。
自己責任となりますが、筆記を受ける時点では、これらの問題は捨てても合格はできるんじゃないかと。あくまで自己責任ですよ。
何故強調するかというと、毎年複線図を勉強しなかった為にギリギリ落ちちゃう方がいるようなんです。
電気工事士第二種の実技試験の勉強方法
第一段階として、筆記試験に合格したら実技試験の道具と材料をいち早く買うこと。
いや、ある程度過去問を本番同様にやってみて、60点超えたなら、筆記試験が始まる前から購入することをおススメします。筆記試験後は中古も結構高くなっちゃいますし、結構品薄になるんですよ。

実際に使った電気工事士第2種実技用のセットです。13問1周用です。足りなくなったケーブルやリングスリーブなどはその都度買い足しています。他メーカーで出しているものよりも部品の数も豊富で、問題集の冊子も付いているので、すぐに始められます。やはりHOZANブランドは強いです。
実技試験は13問で、色々なところで公表されています。頭の中で丸暗記するのも一つの手なんですが、実技は欠陥があると、すぐに不合格。その欠陥となるポイントをまとめてみました。
- 時間オーバーしている。
- リングスリーブの圧着ミス
- 芯線や絶縁被覆への傷
- リングスリーブの破損
- 3路、4路スイッチの配線ミス
- 差し込みコネクタの差し込みが甘い
- 指定されたケーブルと違う
- ねじの締め忘れ
- 端子台のねじの締め忘れ
- ランプレセプタクルの+ー接続間違い
- 丸形コンセントの+ー接続間違い
時間オーバーしてしまう
これは問答無用で一発で不合格です。とにかく試験の制限時間内でしなければいけません。当日、受験者がたくさんいて、慣れない机、慣れない椅子、常に監視している試験官の人達を目の前にしていつも通りできるのか?と言われると、
できないんですよ。ほんとに。
ほんとに一番練習したと言っても過言ではないランプレセプタクルを間違えましたから。
本番の試験では信じられないようなミスをします。
外装を4cm、絶縁被覆を2cm剥かなければいけないところを、何故か10cm剥いてしまいました。そこで気づけば良かったのですが、接続してから気づいてしまい、そこからもう一回外して、ケーブルを剥き直してとやってたら、
終了50秒前でようやく完成。
めちゃくちゃ焦りました。。。
欠陥が無いかを最後に目視で見ていったのですが、全部は確認することができませんでした。ただ、作業中は結構慎重にやったというか、欠陥ポイントや配線などは、その都度目視で確認していたので、完成さえしてしまえば大丈夫だろうと思ってました。
普段の練習では7~10分残して完成するくらいだったんですが、練習の成果が本番で出るかというと、また違うんですよね。。
リングスリーブの圧着ミス
リングスリーブはほんと面倒くさいですよね。これ、刻印ミス結構あります。本番で僕は3回くらい目視で刻印が合っているか確認しながら圧着しました。
3路、4路スイッチの配線ミス
3路、4路スイッチでは、これまでのスイッチの配線と全く別物になるので、一番練習しました。3,4路スイッチを接続する際の独自ルールみたいなのがあるんですが、これは日本エネルギー管理センターさんの動画を見てみてください。
芯線や絶縁被覆への傷
これは、実技本番で気を付けるというよりは、練習で芯線や絶縁被覆に傷をつけないように普段から意識やっていれば、欠陥となるくらいの傷になることは少ないのではないでしょうか?
僕は実技練習、1周目では逐一剥いた後の電線をチェックし、2周目以降は完成後に全部の電線を軽くチェックしてました。
差し込みコネクタの差し込みが甘い
これは、練習不足というよりうっかりミスなので、差し込みコネクタに電線を差し込んだら、必ず奥まで入ってるかを必ずチェックすることを徹底するといいです。
端子台のねじの締め忘れ
ねじの締め忘れというより、しっかり締めずに電線が抜けて欠陥ミスということは、結構あると思います。
ランプレセプタクルの+ー接続間違い
僕は大丈夫でしたが、本番の緊張状態でしてしまいがちなミスかもしれません。接続の際の電線を右周りに曲げることに気を取られ過ぎて、+-への接続をうっかり間違ってしまうと即欠陥となるので気をつけましょう。
電気工事士第二種の実技試験のまとめ
とにかく実技試験の対策は一日でも早く始めること。
学科が終わったらすぐです。CBTで受験すれば、合格したかどうかが試験後すぐに分かるので、できるだけCBTで受験することをおススメします。そうすれば、実技試験まで結構時間があるので、練習に時間を費やせます。
練習する前から欠陥となるポイントなど学ばなくてもいい。あくまで僕のやり方なんですが、勉強などしなくても、動画見てたら勝手に覚えていくからです。
配線接続の方法もやはり、1周目は動画を見ながら練習していく。気になるポイントがあれば、あとで見返せるように、ノートに書いておくと2周目以降楽になります。
例えば、ランプレセプタクルは接続部の絶縁被覆を2cm剥くとか。細かい長さなどもノートに書いておいた方が良いですね。まぁ、僕がしっかりノートに取ってたか?というと、そこまで細かく書いたノートでもなく。覚えの良い人だったら、何も書かなくても十分受かるような気がしますね。
早くから欠陥になりやすいポイントを抑えておけば、3周目には、時間的に余裕ができるようになってきました。僕が考える重要な実技試験のポイントは
- とにかく1日でも早く練習
- 即欠陥となるポイントを気を付ける
- 解説動画をしっかりと見ながら練習
実技の合格率は70%くらいあるらしいので、それほど難しいわけではないです。問題は全て事前に公開されてるわけですから。